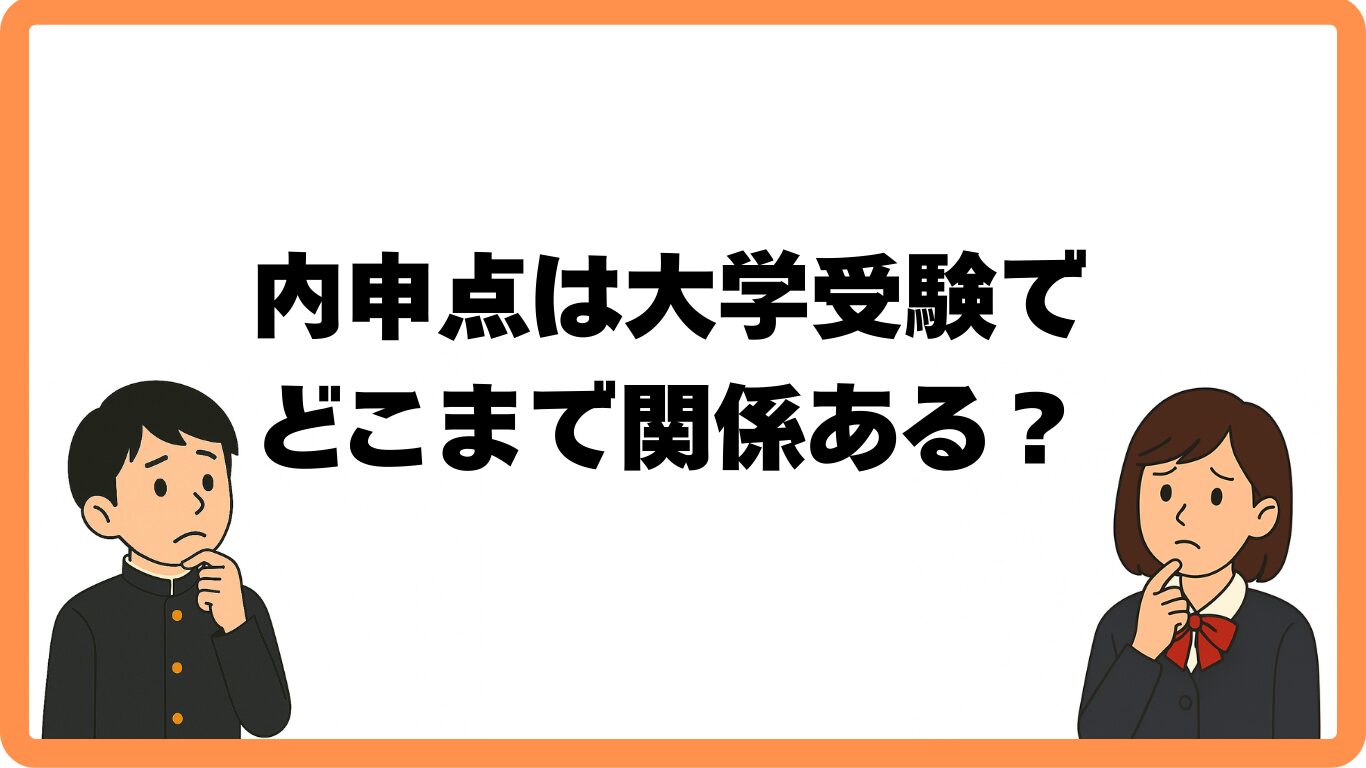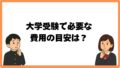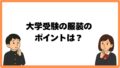「大学受験って結局、内申点は関係あるの?」
「推薦を考えているけど、どれくらい必要なのか知りたい」
そんな疑問や不安を抱えている高校生は多いと思います。
中学では、高校入試において内申点がとても重要でした。その経験があるからこそ、高校でも同じように「内申点を気にすべきなのか」「評定平均はどこまで影響するのか」が気になるのは自然なことです。
この記事では、大学受験における内申点の仕組みや、入試方式ごとの影響度、成績を上げる具体的な方法まで、実例も交えながら詳しく解説します。
さらに「内申点があまり良くない人はどうすればいいか」といった進路対策までカバー。内申点はすぐに上がるものではないからこそ、早めにこうした情報を知っておくことが受験成功の第一歩になります。
内申点と大学受験の関係
大学受験では、選ぶ入試方式によって内申点の重みが大きく変わります。 とくに「学校推薦型選抜」や「総合型選抜」では、内申点(評定平均)が出願条件になっていたり、評価対象の一部になっていたりするケースが多くあります。
例えば、私立大学の指定校推薦では「評定平均4.3以上」が条件となる学部もあり、基準を下回ると出願すらできません。一方、一般選抜では学力試験が中心となるため、内申点が合否に直結するケースはほとんどありません。ただし、調査書として提出は求められるため「まったく関係ない」とは言いきれません。
中学と高校の内申点の違い
中学の内申点は9教科の成績を元に高校入試で使われます。一方で高校の内申点(評定平均)は、大学に提出する「調査書」に記載されます。最大の違いは、「どの入試方式を選ぶか」によって使われ方が大きく変わる点です。
また、高校では教科数が増え、専門性も上がります。美術・音楽・家庭などの副教科も主要教科と同じように内申点に含まれるため、意識しましょう。
内申点の計算方法と評価基準
内申点は、5段階評価でつけられた評定を平均して算出します。例えば「英語4・数学5・国語3・理科4・社会4・音楽4・美術5」の場合、7科目の合計は29なので、「29÷7=4.14」が評定平均です。
評価の基準は学校によってやや異なりますが、以下の要素が共通して重視されます。
・定期テストの点数
・小テストや授業内の確認テスト
・提出物(ワーク・レポート)の完成度と提出状況
・授業中の態度、発言、ノートの取り方
・グループ活動や実技教科での取り組み
普段の授業への姿勢や日々の積み重ねが、確実に内申点へ反映される仕組みです。
入試方式ごとの内申点の影響
内申点がどれほど受験に関係するかは、「どの入試方式で受けるか」によって大きく変わります。 ここでは主要な3つの方式について、それぞれの内申点の扱い方を見ていきましょう。
一般選抜
一般選抜(いわゆる一般入試)では、試験の得点が最優先されます。内申点は合否にほとんど影響しません。
ただし、すべての大学で「調査書(=内申点を含む書類)」を提出する必要があります。多くの場合は確認資料扱いですが、同点の受験者がいた場合に参考資料とされたり、出席状況や生活態度の面でマイナス評価を受けたりすることもあるため、一定以上を保っておくに越したことはありません。
学校推薦型選抜
学校推薦型選抜では、出願条件として「評定平均〇〇以上」という基準が設定されている場合がほとんどです。例えばMARCHレベルの私立大学では、指定校推薦で「4.1〜4.5以上」が求められる学部もあります。
指定校推薦の場合は、高校の成績だけで選考されるため、内申点がすべてと言っても過言ではありません。出願を目指すなら、高1から安定して高評定を取り続ける必要があります。
総合型選抜
総合型選抜(旧AO入試)では、面接や志望理由書、課外活動などとあわせて、内申点も評価対象のひとつになります。
例えば、書類審査で「評定平均が3.5を下回っている場合は選考対象外」としている大学もあります。人物重視の選抜とはいえ、内申点は「コツコツ努力してきた証」として見られるため、できるだけ高い評定を目指すに越したことはありません。
内申点を上げるための方法
内申点を上げるには、「定期テストを頑張る」だけでは不十分です。評価の対象はテストだけでなく、提出物や授業態度、副教科での取り組みなど、さまざまな面が挙げられます。
ここでは、内申点を確実に上げるための4つのポイントを紹介します。
定期テストで得点を取る工夫
テスト前に焦って詰め込むより、1〜2週間前から少しずつ復習しておく方が安定して高得点を狙えます。
とくに暗記科目(理科・社会)以外については、日常的な積み重ねがより重要です。例えば、授業中に「ここテストに出るよ」と言われた箇所に印をつけておき、テスト前にそこだけ集中して見直すだけでも効果的です。
提出物の期限と内容に気を配る
提出物は「出すだけ」ではなく「内容の質」も見られます。文字が読みにくい、空欄が多い、コピー、丸写しのような内容では加点されにくく、評価が下がることもあります。
提出期限も評価項目の対象です。ルーズになりがちな人は、学校の提出予定をスケジュール帳やアプリで管理しておきましょう。
授業態度を意識する
「先生の話をしっかり聞いてノートを取る」「質問されたら答える」「静かに授業を受ける」といった基本的な姿勢が、内申点に大きく関わります。
特別なことをする必要はありませんが、「いつもまじめに授業を受けているな」と先生に思ってもらえるかどうかがポイントです。
副教科の成績も上げる
音楽・美術・体育・家庭などの副教科も、主要教科と同じように評定平均に含まれます。
例えば主要5教科でオール4でも、副教科が3だと平均が下がります。しかし、苦手意識があっても、提出物や授業中の姿勢を工夫すれば「3→4」に上げることは十分可能です。
内申点が低い場合の対策
「もう高1・高2の成績が低くて手遅れかも…」と感じている人も、進路はまだ選べます。内申点を重視しない入試方式や大学を選ぶことで、学力試験での逆転が可能です。例えば一般選抜では内申点を参考にしない大学も多く、実力勝負で合格できるチャンスがあります。
内申点に関する注意点
内申点に対して誤解している高校生も多く、知らないまま過ごすと後悔につながるケースもあります。ここでは、とくに注意したいポイントを3つ紹介します。
1年生からの成績が見られる
多くの高校では、1年生から3年生までの成績すべてが評定平均に含まれます。そのため、3年生になってから挽回しようとしても、手遅れになる場合があります。高校に入った段階から、内申点を意識した生活を送ることが大切です。
副教科も平均に含まれる
副教科の配点も、主要教科と同じです。「勉強ができる=評定が高い」とは限らず、体育や音楽が足を引っ張って評定平均が下がるケースは珍しくありません。通知表に載っている教科は、すべて同じ重みで扱われることを忘れないようにしましょう。
評価に学校差がある
内申点のつけ方には、学校や先生ごとに差が出る場合があります。基準が明確に定められていない部分もあるため、普段からまじめに取り組んでいる姿勢を見せておくことが重要です。「誰に見られても自信を持てる態度」が、最終的にはよい評定にも反映されていきます。
まとめ:内申点を意識して受験準備を進める
大学受験における内申点の重要性は、選ぶ入試方式によって変わります。推薦型・総合型を目指すなら、内申点は大きな意味を持つため、日頃の対策が必須です。また、一般選抜においても、提出書類としての影響はゼロではありません。
大切なのは、自分の志望校・志望学部に合わせて「どれくらい内申点が必要なのか」を知り、そのうえで今やるべきことを決めることです。
高校1年生のうちから意識を変えて、コツコツと積み上げていけば、必ず自分に合った進路が見えてきます。この記事をきっかけに、ぜひ今日から一歩を踏み出してみてください。