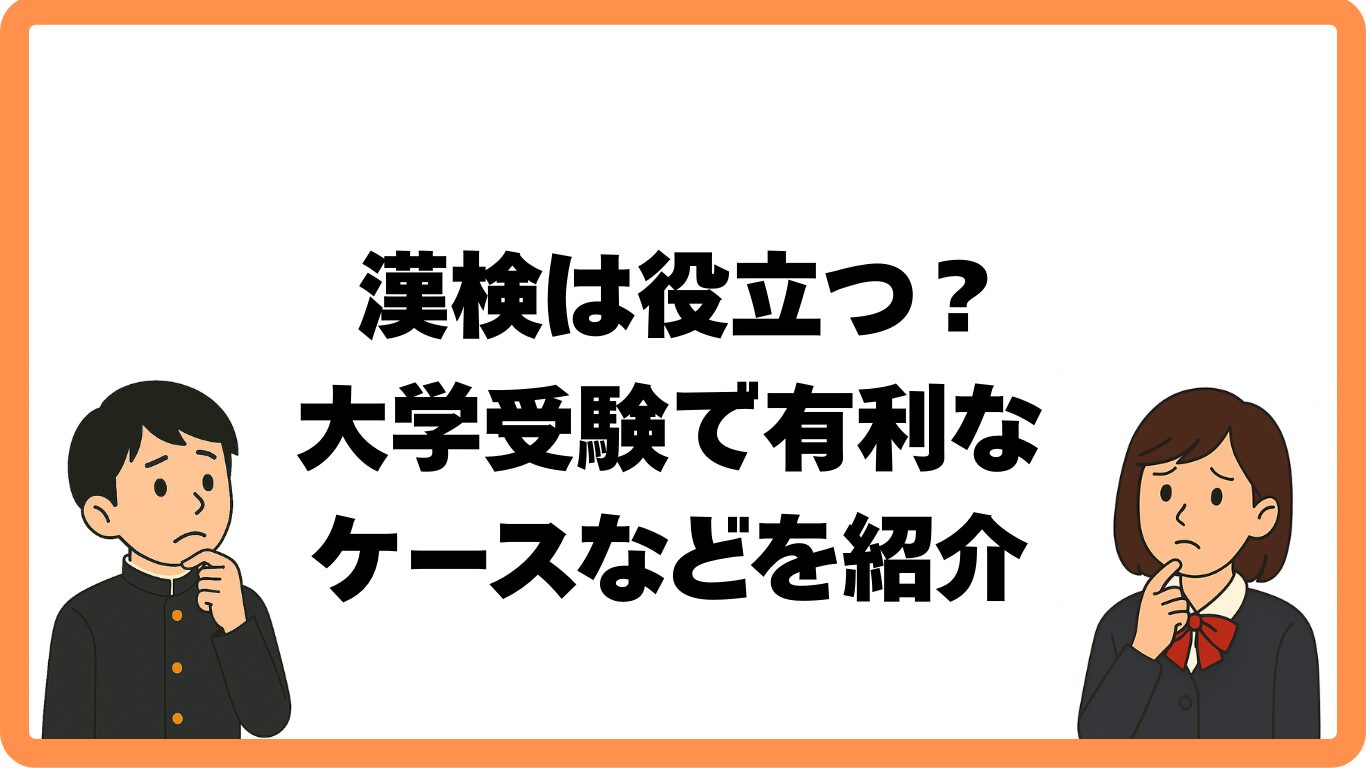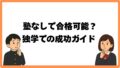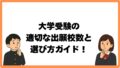大学受験に向けて、少しでもアピール材料を増やしたいと考える高校生の中には、「漢検って役に立つの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
実は近年、漢字検定を評価の対象として活用している大学が増えています。出願要件や加点、合否判定の参考など、さまざまな場面で評価されるため、自分の志望校でどのようになっているか確認しておきましょう。
この記事では、具体的な大学名や制度内容も紹介しながら、漢検の受験が大学受験でどのように有利に働くのかをわかりやすく解説します。
漢検を評価対象に含めている大学は増えている
近年、大学受験において漢字検定(漢検)を評価する大学が増加傾向にあります。公益財団法人 日本漢字能力検定協会によると、令和5年度に「大学受験で漢検を活用している」と回答した大学・短期大学は、全国で721校となりました。
とくに総合型選抜や学校推薦型選抜において、書類審査や加点評価の一環として漢検が活用されることもあります。具体的な活用方法は大学ごとに異なるため、志望校の入試要項を事前に確認することが重要です。
参照:日本漢字能力検定
漢検を取得した際に大学受験で有利になるパターン
漢検を取得することで、大学受験時に次のような形で有利になる可能性があります。
入試の点数に加算される
一部の大学では、所定の級以上を取得している受験生に対して、入試の評価項目として点数を加算する制度があります。 例えば、実践女子大学では、漢検2級以上の有資格者に対して一般選抜で20点が加算されます。
参照:実践女子大学
合否判定時に考慮される
漢検の取得が、合否判定の参考資料として活用されるケースもあります。例えば北九州市立大学では、推薦入試において「漢検+別の資格」を2つ以上組み合わせると加算の対象となります。
参照:北九州市立大学 経済学部
出願要件として定めている大学もある
中には、出願資格として特定の漢検級以上の取得を求めている大学もあります。例えば東京立正短期大学では、外部試験利用型において「漢検準2級以上の取得」が出願条件となっています。
参照:東京立正短期大学
総合型選抜や学校推薦型選抜でも評価対象になるケースがある
漢検は、一般選抜だけでなく総合型選抜や学校推薦型選抜でも評価されることがあります。
これらの選抜方式では、学力試験だけでなく、調査書や自己PR、面接などを含む多面的な評価が行われるため、漢検のような資格がアピール材料として活かされる場面も増えています。
大学受験で漢検を活用する際のポイント
漢検を大学受験で有利に活かすためには、次の点に注意しておくと安心です。
自分の志望校で漢検が評価対象になっているか確認する
まずは、志望する大学・学部が漢検をどのように評価しているかを確認しましょう。公益財団法人 日本漢字能力検定協会が公開している「活用校検索ページ」では、大学ごとの活用状況を調べることができます。
また、仮に評価対象だとしても「〜〜以降に取得したもののみ有効」と記述されているケースもあるため、必ずチェックしましょう。この記述次第では、例えば「中学生のときに取った漢検は時期が古いのでNG」という場合があります。
評価を受けやすい2級以上の取得を目指す
一般的に、漢検が評価対象となるのは2級以上の場合が多いです。例えば実践女子大学では2級以上が加点対象となっています。
他の受験勉強とのバランスに注意する
漢検の勉強は国語力や語彙力の向上にも役立ちますが、あくまで大学受験の一要素に過ぎません。志望校の出題傾向や必要科目に合わせた勉強とのバランスを取りながら、無理のない範囲で取り組むようにしましょう。
また、基本的には高3になったら、漢検の対策よりも志望校の過去問に合わせた受験勉強に取り組んだほうが無難です。
まとめ
漢検の取得は、大学受験において有利に働く場面が確かに存在します。とくに総合型選抜や学校推薦型選抜においては評価の対象となることが多く、志望校によっては加点や出願要件となるケースもあります。
ただし、すべての大学が漢検を評価しているわけではないため、事前に入試要項をしっかり確認したうえで、取得級や勉強量のバランスを考えて取り組むことが大切です。