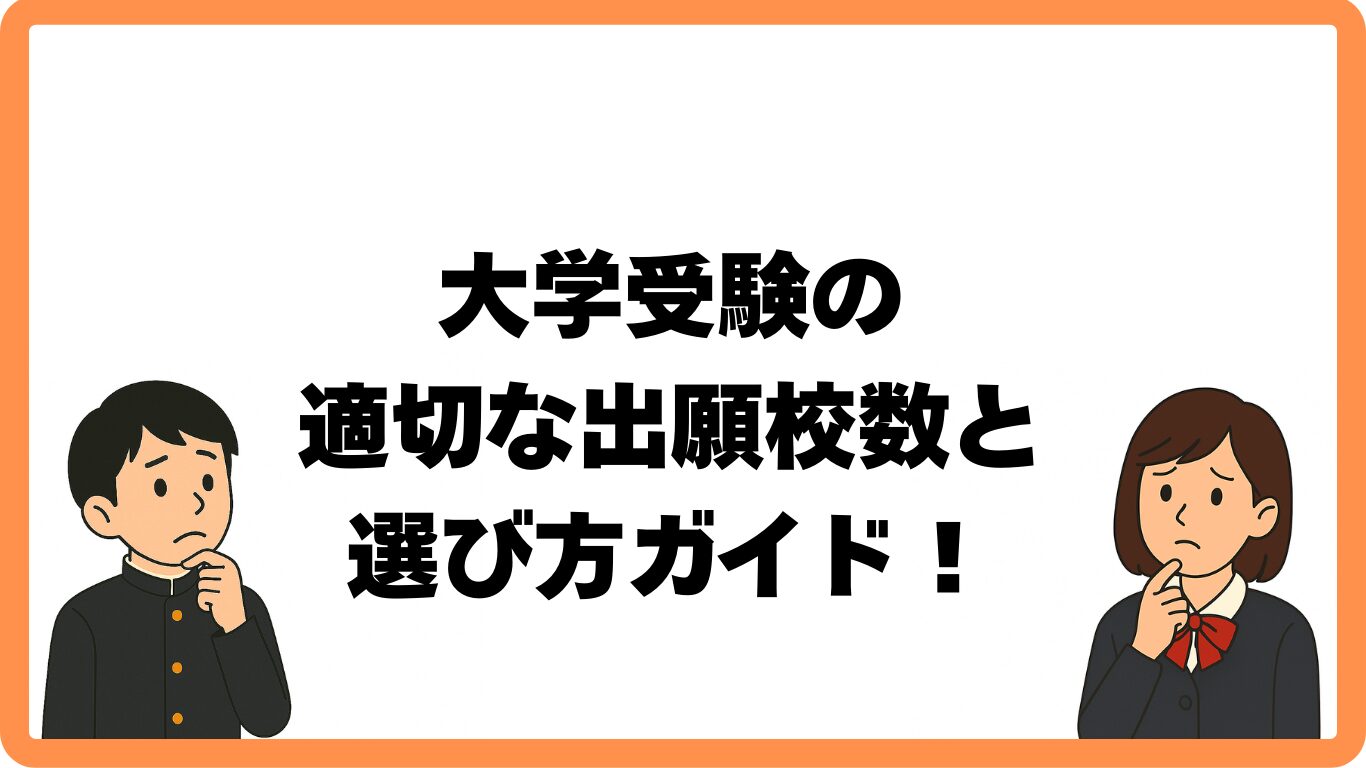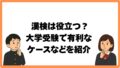「何校受ければ安心できるのか分からない」「受験料や日程が心配」など、大学受験を前に出願校数に悩む人は多いです。結論として、平均は5校から6校程度が一般的です。ただ、学力や経済的な事情によって最適な数は人それぞれ異なります。
例えば、国公立大学を第一志望にする場合は共通テストを利用しつつ、私立大学を複数併願するケースが多く見られます。一方、私立大学を中心に考える場合は、負担を抑えるため3校から5校ほどに絞るケースもあります。安心感を重視するか、効率を重視するかを考えたうえで、後悔のない受験校数を決めていきましょう。
大学受験で何校出願するのが一般的?
多くの高校生は、大学受験でおよそ5校前後に出願しています。出願校の数は第一志望校の難易度や、併願する大学の組み合わせによって変わります。
国公立大学を第一志望にする場合は共通テストの結果をもとに私立大学を追加出願する流れが一般的です。ただし、共通テストが終わってからでは出願が間に合わない大学もあるので注意しましょう。
反対に、私立大学を中心に受験する人は、滑り止めを確保する目的で多めに出願する傾向があります。いずれの場合も出願数を増やしすぎると負担が増えるため、無理のない範囲で調整することが大切です。
何校も受けるメリットとデメリット
出願校数を増やすことで安心感が高まりますが、その分負担も増えます。ここでは、両面をしっかり理解しておきましょう。
何校も受けるメリット
出願校数を多めに設定すると、合格の可能性を広げやすくなります。複数の合格通知が届けば、心理的に余裕を持てるため落ち着いて進学先を検討できます。
また、第一志望校が不合格になった場合も進学先を確保できる点は大きな安心材料です。例えば、国公立大学と私立大学を組み合わせると、進路選択の幅を広げられます。
何校も受けるデメリット
一方で、出願校が増えると試験日程が重なりやすく、体調や集中力の維持が難しくなります。さらに、受験料は1校あたり約3万円かかり、交通費や宿泊費も増えます。合格通知が複数届くと進学先を決める際に迷いが生まれやすい点にも注意が必要です。
必要以上に数を増やすと、学習の優先順位が曖昧になりやすいため、無理のない範囲で計画を立ててください。
第一志望校の決め方と考え方
第一志望校を選ぶときは、偏差値や知名度だけを基準にするのは避けましょう。興味のある分野や通学の負担、学費、大学の雰囲気なども含めて検討することが重要です。例えば、オープンキャンパスに参加して授業や施設を体験すれば、学校のイメージが具体的になります。
学力や生活面、将来の進路などを総合的に考え、自分が納得できる進学先を選んでください。
併願校の選び方と戦略の立て方
出願校を決める際は、第一志望校だけでなく、実力相応校と安全校を組み合わせることが基本です。難易度に幅を持たせることで、どの結果になっても進学先を確保できます。
以下のような組み合わせが目安になります。浪人生の場合は、1段階ずつ判定を上げるイメージです。
| 志望区分 | 校数の目安 | 判定 |
|---|---|---|
| 第一志望 | 1校 | C〜E判定 |
| 実力相応 | 2校 | B〜C判定 |
| 安全校 | 2校 | A判定 |
試験日程や入試方式も整理し、負担が集中しないように調整してください。
チャレンジ校に挑戦するかどうか
チャレンジ校を1校から2校ほど含めると、自分の実力を試す機会になります。合格できれば大きな自信につながります。
ただし、すべてをチャレンジ校にすると不合格のリスクが高くなるため、実力相応校や安全校と組み合わせる方法が現実的です。模試の判定や先生のアドバイスを参考に検討しましょう。
滑り止め校をどれくらい用意する?
滑り止め校は安心感を得るために1校から2校程度確保するのが一般的です。合格可能性が高い大学を選ぶと、心理的負担が軽くなります。
ただ、滑り止めが多すぎると費用と労力が増えるので、必要な範囲にとどめることが大切です。
受験校数を決める流れと手順
出願校数を決める流れを明確にすると、準備がスムーズに進みます。
- 模試結果をもとに志望校リストを作成する
- 試験日程や費用を確認する
- 家族と相談して負担を検討する
- 最終的に受験校を絞り込み出願手続きを進める
上記の流れを参考にして無理のない計画を立てましょう。
受験校数を決めるときの注意点
何校受けるかを決めるときは、学力や費用だけでなく、試験日程や移動距離も確認が必要です。無理のあるスケジュールは体調を崩す原因になります。進学先を決める際の合格発表のタイミングも考慮してください。全体を整理しながら計画することで、落ち着いて受験に臨めます。
試験日程の重なりに注意しよう
試験が連続すると体力や集中力が持たないことがあります。受験スケジュールを確認し、余裕を持った計画を立ててください。移動時間や休息も十分に考慮しましょう。
試験日程については、2日連続くらいまでに抑えておくことが無難です。3日連続はかなりギリギリのラインであるため、注意しましょう。3日連続以上になると最後の日はパフォーマンスが落ちるため、最終日に志望度の高い大学を持ってこないよう意識してください。
受験料や交通費の負担を把握する
出願校が増えると費用も大きくなります。1校増えるだけでも数万円の負担になるため、早めに見積もりを立てて家計と相談してください。事前に準備することで安心して出願を進められます。
複数校を受験する際の勉強スケジュールの立て方
複数校を受験する場合、試験の傾向や科目が異なることが多いです。優先順位を明確にして効率良く学習を進めましょう。共通科目は全体的に対策し、第一志望の特色ある科目は重点的に学習する方法が効果的です。進捗を確認しながら計画を調整してください。
まとめ:自分に合った受験校数で後悔しない選択を
大学受験では何校受けるかは一人ひとり状況が違います。挑戦と安全のバランスを考え、無理のない出願計画を立ててください。早めに志望校をリストアップし、模試や家族の意見を参考にしながら準備を進めましょう。
今日からできることとして、まずは志望校リストを作成し、具体的な出願スケジュールを考えてみてください。