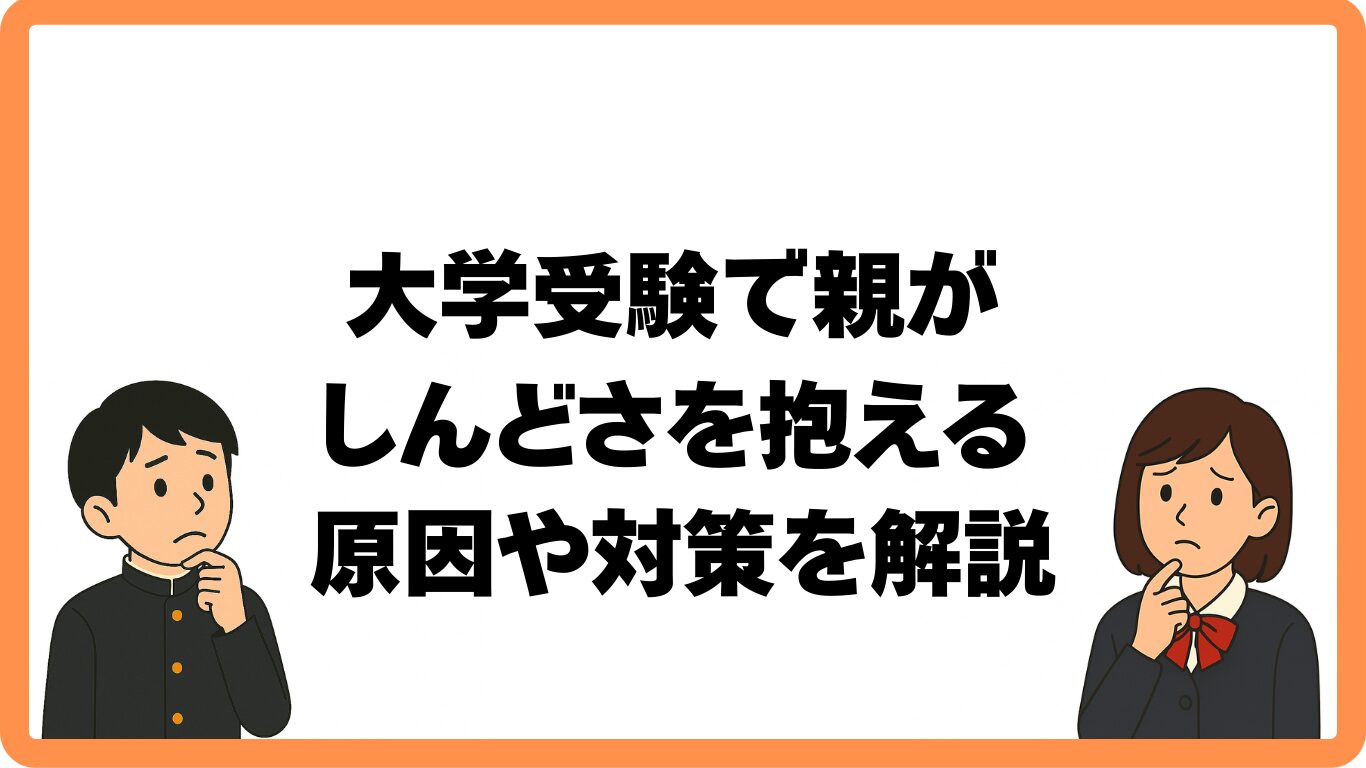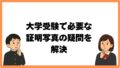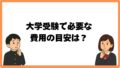大学受験は子どもだけの挑戦ではなく、親も長い時間支える必要があります。責任感の強い人ほど負担を一人で抱え込みやすいです。この記事では、しんどさの原因を4つに分けて整理し、今日からできる行動を紹介します。読み終わったときに「少し肩の荷が下りた」と思ってもらえたらうれしいです。
大学受験で親がしんどい4つの負担
受験の準備は何か月も続きます。その長さに加えて、経済面や情報の多さなど、心が落ち着かない要素がいくつも重なります。ここでは親が感じやすい4つの負担を整理します。どれが一番大きいか考えながら読んでください。
精神的プレッシャー
子どもが希望する大学に合格してほしい気持ちは自然なものです。しかし「合格させなければ」と思いすぎると、親自身も心が張りつめてしまいます。夜になっても「落ちたらどうしよう」と考えが止まらず、眠れなくなることも珍しくありません。
この緊張を少し和らげるために、週に1回子どもの「今週できたこと」「来週やること」をノートに書いて冷蔵庫に貼るのがおすすめです。目に入るたび「少しずつ進んでいる」と感じられます。子どもと一緒に「先週はここまで進んだね」と共有する時間を持つことで、気持ちが落ち着きやすくなります。
学費への不安
親としては、大学受験にあたってお金の心配を感じるものです。受験には塾代、テキスト代、模試代、出願料などさまざまな費用がかかります。漠然と「どのくらい必要なのだろう」と考えていると、「足りなくなるのでは」と不安が膨らみやすいです。
安心するためには、具体的に「何にいくら必要か」を把握することが大切です。支払い予定を表にまとめ、準備が済んだ項目は緑、残っている項目は赤で色分けしましょう。
進捗が目に見えると「ここまで整えられた」と実感できます。あわせて奨学金や教育ローンの相談先も調べておくと、いざというときに落ち着いて対処できます。
情報の多さ
塾や学校、SNS、周りの保護者からも情報が絶えず入ってきます。情報が多いのは心強い一方で、量が多すぎると「どれを信じればいいのか分からない」と混乱しやすいです。この混乱が続くと気持ちが不安定になり、落ち着いて行動しにくくなります。
情報に振り回されないためには、情報源を3つに絞ると安心です。「高校の進路指導」「大学公式サイト」「最新の入試要項PDF」を基本にしましょう。他に気になる話題があれば、ノートに一度書き、週1回だけ見直すルールを作るのがおすすめです。SNSは参考程度にとどめ、最終的に公式情報で確認してください。
生活リズムの乱れ
受験期は夜遅くまでの学習や模試で予定がずれやすくなります。親も寝不足になりやすく、体調を崩しがちです。生活リズムが乱れると焦りも大きくなります。
整えるためには、週のはじめに家族で1週間の流れを決めておくのが大切です。例えば「夕食19時、勉強19時30分〜21時、入浴21時、就寝23時」と決めておきましょう。
家族全員で同じ流れを守ろうとするだけでも落ち着きます。計画どおりに進まない日があっても「7割できたら十分」と考えると気が楽です。
親がしんどくなる4つの原因と今日できる対策
負担を感じる原因が分かったら、できることから一歩ずつ変えていきましょう。1つでも試すことで気持ちが軽くなるきっかけになります。
精神的な負担を減らす
不安や心配を頭の中だけで考えていると、気持ちがどんどん重くなります。週に1回、心配事を紙に書き、声に出して読んでみましょう。「ここは子どもに任せる」「ここは一緒に相談する」と分けるだけで整理できます。
そのうえで「一緒にがんばろう」と伝えると安心感が生まれます。夜寝る前に深呼吸を3回する習慣も、心を落ち着ける助けになります。
学費を「見える化」する
お金の不安は「何にどれくらい必要なのか分からない」ことで膨らみます。受験では、模試料や出願料、入学金、授業料など支払いが多いです。
支払い項目と期限を表にまとめ、緑で準備済み、赤で未払いと色分けすると状況が一目で分かります。奨学金や教育ローンの申し込み期限も合わせてメモすると、準備が整えやすくなります。
情報整理を習慣にする
情報を無制限に集めると、頭の中がいっぱいになります。集める時間は週20分と決め、それ以外は勉強や休息を優先させることを意識しましょう。
SNSで得た話はそのまま信じず、ノートにメモし、週末に公式情報と照らし合わせて判断します。迷ったときは学校の先生や塾の講師に相談するのも有効です。
生活リズムを整える
毎日寝る時間や起きる時間が変わると、疲れやすくなります。1週間の予定を共有カレンダーに書き、同じ時間に食事や就寝を意識しましょう。タイマーを使って勉強と休憩の区切りをつけて勉強させると、子どもも集中しやすいです。家族で「この時間は休む」と決めると、生活にメリハリがつきます。
親が避けたいNG行動5つ
無意識にしてしまう行動が、子どものやる気や自信を奪うことがあります。次の5つは特に注意して避けましょう。
子どもを他人と比べる
ネガティブな言葉を繰り返す
学習計画を親が一方的に決めて押し付ける
SNSの情報を鵜呑みにする
生活を細かく管理しすぎる
子どもを他人と比べる
「〇〇さんの子はもっと成績がいい」と比べられると、子どもは「自分はだめだ」と感じてしまいます。比較ではなく「先月より10点伸びたね」と本人の努力を認める言葉がやる気につながります。小さな進歩も言葉にして褒める習慣を作ってください。
ネガティブな言葉を繰り返す
「どうせ無理」と言われると、挑戦する気持ちが弱まります。ネガティブな言葉は子どもの意欲を奪いがちです。「次は何を変えてみようか」と未来に目を向ける声かけを意識しましょう。話すときは落ち着いた声で伝えると安心感が生まれます。
学習計画を親が一方的に決めて押し付ける
学習計画を全て親が決めると、子どもは「どうせ親が決めるから自分で考えなくていい」と感じやすくなります。この感覚が続くと責任感や自主性が育ちにくいです。
計画は子ども自身が立て、親は相談を受けたときだけ助言をする程度にとどめましょう。週に1回、計画を一緒に見直す時間を作ると安心感が生まれます。
SNSの情報を鵜呑みにする
SNSには多くの体験談が流れていますが、正しいとは限りません。見すぎると「うちの子は遅れているのでは」と不安が大きくなります。情報は一度ノートに書き、公式サイトや学校で確認してから判断しましょう。
生活を細かく管理しすぎる
親が生活を細かく管理すると「信用されていない」と感じやすいです。基本的なルールだけ決め、細かい部分は本人に任せてください。任されることで責任感が育ちます。
子どものやる気を育てる5つのステップの声かけ方法
子どもが挑戦を続けるには、安心感と自主性を育む声かけが大事です。次の5つのステップを試してみてください。
ステップ1 子どもの話に耳を傾ける
最初は話をさえぎらずに聞くことに集中します。うなずきながら最後まで聞くと「受け止めてもらえた」と感じ、安心感が育ちます。
ステップ2 小さな成果を具体的に褒める
「すごいね」だけでは何を褒められたのか分かりにくいです。「単語50個覚えた努力が結果につながったね」と具体的に伝えると自信が育ちます。
ステップ3 一緒に計画を立てて見える化する
計画を共有すると「進んでいる実感」が持てます。カレンダーに書き、週に1回短い時間でも振り返る時間を作りましょう。
ステップ4 失敗を次に活かす
失敗を責めず「何が難しかった?」「次はどうする?」と一緒に考えます。紙に書き出すと整理しやすいです。
ステップ5 最終決定は子どもに任せる
最終的な進路や学習の選択は子どもが決めます。親は応援役に徹し、決めたことを支えると安心感が生まれます。
まとめ―笑顔の親がいちばんの応援
大学受験で親もしんどいのは自然なことです。負担を整理し、小さな行動から試せば心も軽くなります。親の笑顔が子どもの安心につながります。できるところから一歩ずつ始めてください。